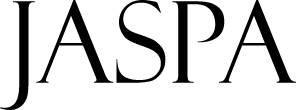経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課長との座談会

日時:2024年2月28日(水)10:30~12:30
会場:全国ソフトウェア協同組合連合会 会議室
出席者:
【経済産業省】
内田 了司(商務情報政策局 情報技術利用促進課長)
【全国ソフトウェア協同組合連合会】
安延 申(会長)
林 知之(副会長、東京システムハウス株式会社 代表取締役)
太田 貴之(副会長、株式会社エー・アール・シー 代表取締役)
2024年の経済産業省の施策と今後の展望 / ビジョン

会長
(安延) 内田課長はまさに情報政策のコアを担っておられる方ですが、まず、2024年度の経済産業省の重点政策や、課長が重要と考えられていることを簡単にご紹介いただけますか。
(内田) 広くデジタル政策全般としては、社会のデジタル化が加速度的に進み、必要とされる計算基盤の量が急激に増えています。そこに昨年から大きな話題となった生成AIのような新しいテクノロジーが登場しています。半導体はAI開発や活用の基盤でもあり、計算能力の質の高度化も求められています。地政学上も重視されるようになったこうした計算基盤へ最大限の政策資源の投入が続いています。次世代半導体のラピダスを始め日本の半導体政策や支援策への期待から、日本に対する投資意欲が高まっています。この流れは継続する必要があります。加えて、ドローンや自動運転等の社会実装に向けて、デジタル時代の社会インフラとして共通規格に準拠するデジタルライフラインの全国的な整備を進めています。最初の東京オリンピックを契機に高速道路網など社会インフラが急速に整備されたように、今まさにそのデジタル版でドローンや自動運転のような次世代の社会インフラが整備されようとしています。また、そうした産業を支えるデジタル人材の育成も、政府全体で高い目標を掲げて関係省庁が連携して、また民間の新規参入も促しながら、官民で人材育成に取り組んでいます。
こうしたデジタル基盤を活用してデジタル経済のパイを大きくしていく上で、皆さんの業界がどのくらい活躍するのか、
デジタル基盤の上のレイヤーでどういうアプリケーションが走るか、これこそ皆さんの業界とダイレクトにリンクする問題でもあります。
ソフトウェア産業や地域のITベンダー、IT企業との関係では二つのトピックがあります。一つは生成AIです。1年ほど前にChatGPTが出てきて自然言語でAIが操れる時代に入り、既にプログラマーがコードを書かせて生産性が何割も上がっているといわれています。そうなるとこれまでのソフトウェアやシステム開発のあり方や大手の商慣行は変わらざるを得ません。そのときに全国各地の中規模、小規模のソフトウェア開発企業は、次はどこに仕事を求めていくのかを今から考えておく必要があると思います。われわれも一緒に考えたいと思いますが、特に遅れが目立つ地域企業のDXをもう一回見つめ直す必要があると思います。
中小企業庁の統計では、地域企業でデータを活用して新しい業務を始めるなど、本気でDXをやっているところは4%程度となっています。ちょっとしたデジタル化で生産性が上がることは地域企業の方にはまだまだ知られていません。特に人材や資金に乏しい中小企業にDXと言っても難しいと思うので、これからは地銀などの地域の伴走役にDX支援に取り組んでもらうべきという議論があります。地域のIT関係者がこうした取組に参加してもらうことを期待しています。
(注)3/27公表DX支援ガイダンス(以下サイト参照)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dxshienguidance.pdf
もう一つは、人材不足です。今はどの業界でも人材不足が顕在化していますが、そもそも生産年齢人口が構造的に右肩下がりの状況は2000年以前から始まっていましたし、高齢者や女性の社会・労働参加も含めて働ける人は働いているという状況で、労働量を増やすことは困難です。そうなると、今既に社会で働いている人たちの労働の質を高め、社会全体で生産性を上げていく必要があります。
リスキリングでは、生成AIも含めて新しい技術への理解を深めることが大事ですが、社会人一般にまだまだデジタルのリテラシーが足りないということで、ITパスポート試験の受験が社会人レベルで増えています。普通の事業会社、特に金融・保険業を中心に、デジタルのリテラシーを身に付けないと、社内で飛び交うデジタル・ビジネス用語についていけないという意識は高まっていると思います。生成AIも含めて新しい技術が登場する時代です。大学を卒業したら学ぶのは終わりではなく、全ての社会人にとって学び続けることが必須というのが当たり前の時代になっています。実際、大手から中小まで常に人が採りにくい状態が続き、ITエンジニアの中途採用も簡単ではなく、従来よりも高額で、見つかったとしてもかなり高値が付くようになっています。中途採用の玉が減っているということもあるでしょうが、既に大手では、DXを進めていく上では社内業務に精通したデジタル人材を育成した方が良いという人材育成の内製化へと動き始めています。
こうした変化の先で、地域の中小・中堅のIT企業は今後どうするのか。この瞬間はまだコロナで止まっていた仕事の余波、人手が足りないこともあって、需要超過の状態で景気はむしろ非常に良いのでしょうが、これまでの業界の歴史的変遷を振り返れば仕事の内容が変わらないと考えることはリスクです。だからこそ、リスキリングは大手企業だけでなくソフトウェアやITシステムに関わる全ての人々の課題です。今は過渡期的にCOBOLを使える人が重宝されているとよく聞きますが、それは10年以上続くのでしょうか。
新しい技術によるビジネスの変化は、明日急に起こるのではなく徐々に技術が浸透していく中でじわじわと起こってくるので、今は足下のビジネスをしつつ、10年後に企業としてどうあるのかということを考えるタイミングだと思います。
産業構造や企業構造への影響

副会長、東京システムハウス株式会社 代表取締役
(林) おっしゃるとおりコロナで止まっていたこともあり、2018年のDXレポートにおける「2025年の崖」のインパクトもあって、今は猫も杓子もDXで、当面は本当に仕事が豊富だし、引き合いも多い反面、とにかく人が足りないというのが現状です。
問題なのはやはり人手不足で、AI(DX含め)は一つの産業革命のようなものですから、生産性が上がっていく中で、なくなる仕事も出てきます。スキルアップして上にいける人もいるけれどもそうでない人もいて、質の高い仕事、レベルの高い仕事は日本人中心になるかもしれませんが、ブルーカラーの仕事も必ずあって、そこを日本人で補うのか外国人を入れるのか。当面はオフショアを使うなどして人手を確保しなければいけないのだろうと思っていますが、10年後、20年後を見て今何をしておくべきかはまだ考えているところです。
弊社はキーパンチから始まった会社なのですが、入力したら次にデータ処理があるということでシステム開発に移っていき、金融系を中心に大型汎用機の技術者(SE・PG)を派遣する形で事業が拡大していきました。バブルの時代には社員80人の会社が僅か4年で300人を超えていましたが、バブルがはじけて半分以下になりました。そのときに、創業者である高橋が、もう単純な人出しの下請け仕事はやめよう、創業の理念である自分たちの商品やサービスで直接お客さまやマーケットと対峙しようと決意して、1992年以降、ソフトウェア開発を始めました。最初に手がけたのがゴルフ場の総合運営システムで、今、全国の200を超えるコースに入っています。銀行・保険などの金融関係もベースとしてずっと続いていて、今も絶好調です。それから、私が1995年から担当したのが、アメリカの会社が作ったオープン系のCOBOLを輸入してそのプロダクツを販売するというビジネスと、日立、富士通、日本電機、IBMの自動変換ツールなどを作ってクライアントサーバーに持っていくレガシーマイグレーションサービスで、2000年問題が追い風にもなって、144社の代理店になって成長してきました。
その後、プロダクツの輸入販売はなくなり、マイグレーションサービスはクラウドに移行して、COBOLソースコードのままJAVAの環境を生成するCOBOL 4Jのようなものも発売するなど、渋くニッチなところですけれども、非常に仕事が多い状態です。内田課長はCOBOLが10年後も続くかとおっしゃいましたが、COBOLはできてもう60年で、60年続いたものがなくなるものではないと思っています。それが事業の一つの柱になっていますし、あとは食品表示法ができた20年近く前からは食品業界の成分管理システムの開発を始めて、今はメジャーどころではヤクルトや石屋製菓、エースコック、シャトレーゼなどでご利用いただいています。
KDDI総合研究所サポートも長年していて、研究所のいろいろな技術をもっと世に出して社会貢献もしたいしビジネスにもつなげたい、アプリケーションの世界はノーコードのAIも出てどんどんシュリンクしていきますが、IoTの世界は自動運転などを筆頭に今後どんどん広がるということで、2001年にKT-NETという任意団体をつくりました。ただ、やはりハード絡みの分野でわれわれはあまり経験のないところですし、ハードをやろうと思うとまずは投資が必要なので、まだそんなに大きなビジネスはできていないのですが、方向性は良いということで60社ほどに入ってもらって活発にやっています。
あと、ここ3~4年伸びてきているのがRPAで、当社は端末側ではなくサーバー側で、イギリスのBlue Prismの製品を販売しており、金融系にはだいぶ導入が進んでいます。
やはりキーワードは人手不足と、大きなところではバブル崩壊による生産性や付加価値の向上で、今はRPAという表現はしないようにしているのですが、自動化のところが動いている状況で、それによりバブル前には300人で19億円だった売上が今は200人で38億円と一人当たりの売上が3倍ほどになっています。
(太田) 弊社は1980年創業で、データエントリーから始め、現在はITインフラの設計から構築、運用保守が8割くらい、ソフトウェア開発が2割くらいになっています。取引先は大手Sierやメーカー様で、受託業務が中心となっており、林さんの会社のように自社製品やサービスの展開もできるように頑張っているところです。
うちクラスの会社だと、経験者を中途採用しても結局辞めていってしまうということで、弊社ではずっと新卒か異業種からIT未経験者を採って育てるようにしていて、それにより育成のノウハウがたまってきたものですから、少しずつではありますが教育事業という形で自治体とのお付き合いなど、広がりを見せてきています。現在、売上は社員240人で28億円、1人当たりの売上は高まってきているかなというところです。
やはりコロナのインパクトはとても大きくて、今起きている変化にも関わってくるところですが、テレワークをやれる環境はそろっていながらなかなか動かなかったのがコロナによって一気に進んで、ルールは外部環境によって変えられるということをすごく感じた4年でした。コロナでなくなる仕事もあれば生まれる仕事もあり、いい意味でも悪い意味でも働き方の変化があって、現在に至っているというところかと思います。
人の話も少ししますと、人はすごく採りにくいです。社員一人を採用する単価も今は倍、あるいはそれ以上になっていますし、逆に流出の方も対応が大変で、せっかく採用した新人が何年か育てると大手に行ってしまうということで、日々疑問も感じながら経営しています。
(内田) 今の人材流動については、私も人材育成に関わっていて思うところが多々あります。転職のミスマッチもよく聞くところです。
やはり長い目で見て、どちらかというと労働者目線で、大手でも中小でも自分のスキルと仕事、賃金が適切にマッチするという方向に向かわないと、本当の意味での人の最適配置は実現しないと思います。
デジタルスキル標準を作った背景にはそういうところもあって、スキルアップを通じて自分が就きたい仕事に就けるようにするという未来を実現するためには、あるいは組織の中で人材育成をする場合でも、個人が持っているスキル情報がどこかに蓄積され、それが継続的にアップデート、さらに、求職情報と適切にマッチングされ、適正な年収水準も見える化されるべきだろうと思いますし、それがスキルアップのモチベーションでもあり、適材適所の仕事に就くということの究極的なゴールなのではないでしょうか。採用する企業側はその人が本当に求めるスキルを持っているのか、働く側は自分のスキルに合った面白い仕事ができるのか、ふたを開けてみないと分からないという状況は、解消しなければいけません。

副会長、株式会社エー・アール・シー 代表取締役
生成AI―まずは使ってみて、使い続ける
(内田)ところで、お二人の会社の発展の歴史を伺うと、会社が発展していく過程で当然技術の変化があり、徐々に新しい技術を取り入れていって常に新しいビジネスを立ち上げてきている。その過程でエンジニアがスキルアップしたり、スキルを持っている人を外から採ってきたりして、過去50年ほど最先端の技術に対応しています。そういう経験をもってすれば、今の生成AIへの対応も自然とできていくのでしょうか。
(林)われわれはAIそのものを作る立場ではないので、それをどう活用して、それぞれの仕事の中にどう組み込んでいくか。プログラミングもそうですし、例えばゴルフだとダイナミックプライシングでいかに適切な価格で提示するかなど、いろいろな場面でそれを利用するというのがわれわれのポジションで、ユーザーはそれを知らないうちに使っている。そんな時代になるのではないかと社内では話しています。
もう一つ、1、2年ほど前から取り組んでいるのがデータでカスタマーデータプラットフォームの構築とその後それをどう活用するかで、そこには必ずAIが絡んできます。

商務情報政策局 情報技術利用促進課長
(安延) 私はメディアの責任はすごく重いと思っていて、例えば生成AIなどと言うと何かすごく新しい技術のような気がするのですが、本質は昔から言われていたAIであって、その基本技術、コア技術は、経済産業省が力を入れておられる半導体とネットワークの高速化とセットだと思っているのですが、要は世界中が過去1000年間蓄積してきたような事例と知識を全部瞬時に見て、コンピュータ上で試行錯誤を繰り返させて、この解が一番良さそうだというものを導き出してくる。ただ、どんどん新しい事例が積み重なっていくので、出てくるアウトプットもその時々で変わってくるという、まさに人間の頭がやっているのと同じことをコンピュータがやるだけなのです。ただ、そのスピードが著しく速くなって、人間の脳に近づき、分野によっては超えてきているというのが現状ではないかと思っています。
ChatGPTやAIも極論すると超賢くて大量のデータを処理でき、かつ、その結果が時々刻々と改善されていくということです。例えば、業務処理プロセスをシステム設計に落として、概要設計をして・・といった上流工程は、「ユーザーが自分で出来るじゃないか」となって大きな影響を受けるかも知れませんが、私の個人的な意見ですが、JASPAのプレーイングフィールドは、AIの進歩があっても案外市場変化は少ないのではないかと思っています。例えば、お客様のシステムをモニターして異常があると直ちに対応してリカバーするといった業務は、大手元受けが高い給料を払って自社でやっている例は少ないと思います。大体下りてきて我々くらいの規模の会社がやっているのですが、日本の企業や公的団体は責任者は誰だと叫ぶのが好きなので、「AIがやっています。以上、終わり」では済まされない。よって、その仕事は案外なくならないのではないか?逆に今は高度だと思われている、例えば人事評価などたくさんの人がすごく労力を使ってやっているような仕事は、生成型のAIが進化すれば、あっという間に置き換わっていくのではないかと思っています。要するに、一番置き換わるのは「システムの仕事」じゃなくて「ヒトの仕事」ではないでしょうか。
(太田) それで言うと、僕は生成AIというのは1995年以来、要はWindows95とインターネット以来、もしくはそれ以上のインパクトに十分なり得るパワーを秘めているという話をしていて、何が変わるかというと、頭の使い方です。仕事でも、過程はAIがやってくれるからいいのだけど、ここというところでわれわれの出番がある。生成AIも、学習のさせ方でいくらでも答えは変わってくるわけで、そこでの頭の使い方が変わってきますし、林さんも言っていましたが、われわれIT業の根幹を成すデータをどう拾い、どう分析するかというところの技術、ここでの頭の使い方が今後求められると思っています。
(内田) 生成AIは、安延さんがおっしゃったとおり、膨大なデータを学習したモデルで、問いに対して前後の文脈から最適な回答を選ぶもので、それは思考というよりも学習の結果です。一方で、太田さんが言われた1995年以来、あるいはそれ以上のインパクトがあるというのは私もそのとおりだと思っていて、生成AI自体が日々進化しています。生成AIの利用に関して本当の意味でアドバンテージを持っている人はまだ少なく、ある意味スタートは横一線で、むしろこれから情報をキャッチアップして使い続けているかどうかで、半年後、1年後には使っていない人とは相当大きな差が出てくるものと思います。使い続けることで生成AIはこういうものだなという自分なりの評価ができてくると思うので、今この瞬間に生成AIはこういうものだと断定する必要はないと思います。むしろ便利なツールが出てきたのだからまずは使ってみて、そして使い続けることが大事だと思っています。
政府全体では、昨年5月にAI戦略会議が東大松尾先生を座長に立ち上がり、早速、課題・論点を整理して、各省庁が法解釈の明確化やガイドライン作成に取りかかりました。当課でも生成AI利活用人材のスキルについて整理を行いました。ハードの面でも国産LLMの開発を国も支援していて、これから汎用型と特化型で様々な特徴をもつLLMが使えるようになり、生成AIの社会実装に向けた選択肢は広がると思います。昨年来、多くの会社が生成AIを導入していますが、社内業務効率化に使ってはいるけれども、新しい製品やサービス開発にまで繋がった事例はまだ多くありません。政府も利活用に向けた環境整備に取り組んでいるので、生成AIの登場をきっかけにDXが加速することを期待しています。
(注)LLM=Large Language Mode大量のデータとディープラーニング(深層学習)によって構築された言語モデルのこと。AIが自然言語を理解し、処理していくために必要であり、前提となる。Google社が発表したBERTやChatGPTで知られるOpen AI社のGPT等が著名である。
(安延) でも、こういう言い方は申し訳ないですが、JASPAの会員企業は端的に言えばそんなことになど関心はないわけですよ。ある日突然AIの世界が出現してきて、例えば司法試験の問題を解かせると、多分あと5年たったらAIは人間のどんな優秀な受験者よりも良い点数を取るようになるでしょうが、われわれのような法律の素人からすると、既得権者が文句を言ってそれを止めるなよと、言いたいわけです。例えば、いま、非常に難関とされる司法試験というのは法律の条文と過去の膨大な判例の中から最適なものを選んできて回答を出している訳で、それをひたすら何年も勉強した人が司法試験に通って弁護士や判事、検事になるという仕組みなわけです。しかし、こうした作業は、実はAIが一番得意なところでもあります。このような分野はほかに山ほどあります。要するに、世界はもう変わりつつあって、こういう変化に如何についていき、リードするかが非常に重要な時に、変なノイズを入れて、ただ足を引っ張るというのは止めてほしいという話で、司法制度を例に挙げましたが、他の分野でも似たような話は沢山あると思います。このあたりは、「純粋デジタル」の話ではなくて、アナログの制度を国はどうしていくつもりなのか・・と密接にかかわってきます。JASPAに参加しているような中堅、中小以下のソフト会社などからすると、このあたり政府が何を考えているか見えないよなというところはあります。
あと、林さん、太田さんもおっしゃったようにもう一つよく分からないのはデータの取り扱いです。いまのAI、例えばChatGPTがどんなデータを食っているのか分かりません。他方、文化庁や一部の著作権保有者が言っている著作権のあるデータをAIが勝手に使うことは一切許さないというような話もあります。しかし実際にそのような保護が出来るものでしょうか?またすべきだとも思いません。全体がアナログの経済活動を前提に出来上がっている既存の制度や業務などに影響が出てきたときに政府はどうするのかという、すごく基本的なところに関する考え方があまり示されないままに走っているなという感じはあります。
(内田) 政府が法解釈やガイドラインに取り組んでいるのは、既存制度によって生成AIのような革新的な技術の活用が妨げられないように、更にはそこから生じうるリスクに対応するという観点で取り組んでいるものです。これまでも、一昔前の高性能コンピュータの能力をもつ端末が今日ではスマホとして個人の手に行き渡り、それによって仕事や業務のやり方が大きく変わりましたが、人々は自然とそれに対応してきています。私も太田さんのおっしゃるとおり1995年以上のインパクトがあると思っています。それだけに生成AIを学ぶ使う人と使わない人で差がうまれることがあり得ます。生成AIの普及や進歩によって仕事の選択肢が増える、個人であれば一段ステージを上げた仕事のやり方ができるでしょうし、エンジニアであればコードは丸ごと書かせてそのチェックにむしろ注力するように、機械に任せられるところは任せて、人間はより自身の成長のための時間の使い方が大切になってくるのではないか、という話しを生成AIの活用に先行する人達から聞いています。
いずれにしても、特に経営者レベルで考えるべきことは、もう使うことは前提にして、使えば必ず効率化されて、これまでの業務が代替されるでしょうから、そこに関わっている人たちに何をしてもらうかということです。皆さんの業界ではこれまでお客さんの自動化・効率化をお手伝いしてきただけでなく、自社でも自動化・効率化を図ってこられたと思うので、今回についても自然に対応が進むのではないかと思いますが、やはり目に見える変化はこれまでよりも大きいという意味で、1995年以上のインパクトがあるというのは、その通りだと思いますね。
地域におけるデジタル人材の確保とITの地産地消
(林) そうですね。話を戻すようですけれども、転職サービスは行き過ぎですよね。
(安延) 確かに、現場で必死になって一生懸命ものを作っている人が1000万円を超えるのがすごく大変なときに、人の紹介といってAとBをつなぐだけ、あるいは紹介するだけのエージェントがみんな年収2000万円とか2500万円というのはおかしいですよね。
(内田) 日本ではITエンジニアの処遇が良くないと言われているところ、今日これだけ人材不足が社会問題として言われているのだから、エンジニアにちゃんとお金が行っているなら良いのですが、情報を握っている側だけが儲けているのだとしたら、それは違うよなという気はしますね。
(林) そういうやり過ぎなところには少し規制をかけるようなことと、われわれの方もスキル標準なども出して、こういう仕事だったら幾らですよというようなことを発信する努力も必要だと思います。
(内田) 採用数が多い大手の採用慣行が変わること、特にデジタル人材についてはスキル標準もあるのですから、スキルベースで採用し、スキルに応じた職能給がある、スキルベースで学びながらスキルアップしていく、人材の確保や育成はそうした方向に向かうべきだと思います。そのためには個々人のスキル情報が情報処理技術者試験の合格情報も含めてしっかりと蓄積され、必要な時にそれを活用できるようなスキル情報基盤が必要です。IPAともそうした議論を始めています。
IPAは半世紀に渡って情報処理技術者試験を実施した膨大な受験者の情報がありますが、それが十分活用されていません。
いま、デジタル人材の不足が社会課題となっています。デジタル技術の進化のスピードに着いていくためにも、個人レベルでも組織レベルでもスキルベースでの人材育成が定着するようなエコシステムの実現に取り組んで、継続的な学びの文化を醸成していきたいと思っています。
(安延) 今や組合であることのメリットが少なくなっている中で、数少ない、残っているはずのメリットが、単独企業では応募できないようなスキル向上のための補助金事業にJASPAベースで応募できることです。ところが、わざわざ使いにくい制度にしているのではないかと思うところがあるのです。リスキリングのための教育プログラムに数日、あるいは1週間フルに参加しなければ駄目だと言われたら現場で働いている人間の稼働が減ります。となると、そもそも売上を減らした上に研修費用の2分の1は会社負担になってしまいます。それなら同じ予算を使うのであれば、対象人数は半分でいいので補助率を100%にしてもらえないかという話があります。また、やりたいという会社がいるのだけど最低人数に届かなくて、仕方がないから太田さんなどが苦労して自社から人を出すという努力をしている本末転倒のようなケースもままあって、そういうこまごましたところでの要望はいっぱいあります。
あと、公共調達はAIの時代に結構重要だと思っているのですが、全国一律の調達制度というか資格というか、枠組みがもうここ40年変わっていなくて、私が経済産業省の課長だった頃から公共調達の6~8割がトップ4社で占められていて、それは今も変わっていません。自分の力不足を棚に上げてしまうのですが、過去の納入実績を過度に重視したり、システム費用の支払いが完成し、検収を終えるまで支払われず、1年間は自分で資金繰りして下さいという仕組みです。こうなると、その間の費用を負担できる会社しか応募できないわけで、JASPAの会員のような中堅企業、中小企業は最初から参入は無理です。大手と同じ実績、同じ費用負担能力、同じ資金調達能力を求められれば、太刀打ちできるわけがないですよね。地方は特に応募すらできない状態で、公共事業でも土木や建築は支払いを年4回に変えていると承知していますが、今や最も遅れているのがデジタル業界です。

(内田)例えば林さんのところは、もう下請けはやらない、自分たちでビジネスを開拓していくということで、お客さんのデジタル化やDXなどのニーズを聞きながらシステムを作っていったということですが、そういうことは地方の企業でもできるわけですよね。
(太田) 地域企業のDXが進んでいないという話かと思いますが、私は地域の一番の大企業はそこの自治体だと思っていて、自治体のDXが進み、自治体の仕事に地域の企業が入っていけるようなスキームなどができてくると、意外とITの地産地消が進んでいくような感覚は、幾つか自治体を回っている中で感じます。
(林) あと、われわれ業界としては、オフショアは前からやっていますが、やはり外国人も採用していかないと人が足りない。その意味ではビザ、資格の問題がありますよね。
(内田) 外国人ニーズはどのくらいあるのですか。
(林) うちはエージェントを使ってインド人を直接向こうの大学から新卒で採ったり、JASPAにインド人の社長さんがいて、そこを使うことによってよりいいものをより安くという形で動こうとしていますし、4月には中国人が2人入ります。
(内田) 日本でも全国の大学が社会のニーズに応えたいということで情報やデータサイエンスに注目していて、文部科学省も昨年、過去何十年間も変わらなかった情報学部の定員を3割くらい増やしています。例えばJASPAとそういう地域の大学で個別に連係して、もう少し日本人をリクルートするというやり方もあるのですかね。
(安延) JASPAの下部組織の会員企業に聞くと、高専が採れれば御の字で、そもそも大卒なんか採れませんと言います。役所として悩ましいのは、教える先生がいないという話もよく聞きますよね。
(内田) そうなのです。だから、特に地方の私大などで、コンピュータサイエンスを教えたいのだけれども先生がいないというところのお手伝いを地方の会員企業にもご協力いただき、それをきっかけに経済界と大学のパイプをつないでいくことが期待されます。
(太田) そこでシニアの人たちに活躍してもらえれば、われわれとしてもいいですよね。
(内田) いずれにしても大学は本当に必要な分野の先生が足りないのですが、それ以上に実践的な経験の機会を用意することができていなくて、大学側はむしろその意味で企業との接点づくりをしたいと考えているのだと思います。
(林) 熊本大学がそういう講座を開設していますよね。
(内田) そうです。あそこは産学官が一体となって半導体人材の育成をしています。私たちは半導体人材でなくても普通にデジタル実装、ローコードツールを使ったらこんなことができますよというようなところを全国の情報学部、学科でやりたいと思っていて、意欲的なところは大学から直接地元の産業界にリーチしてやっていたりするのですけれども、そういう連携ニーズは全国各地にあるのです。
(太田) 岩手県立大学にはソフトウェア情報学部があって、学長が門前町構想で地域と一緒になってやっていくと言っていますが、そういう動きが広がっていくといいですよね。
(林) それに、せっかくGIGAスクール構想でICTの活用を推進しているのですからね。
(内田) 地産地消のような発想で地域企業と大学との連携のニーズは結構あって、高校でも情報Ⅰが必修になってレベルの底上げが図られているので、それを大学や社会にまでつなげていくという意味でも全国の高等教育機関での情報教育の充実が期待される時代になっています。経済産業省でも地方大学ブロックごとに地域ベースでマッチングしていこうという話をしているので、またぜひ相談させてください。
(林) われわれは業界としてそこに講師を派遣して協力する。
(安延) 卒業生の採用も。
(内田) そうですね。地域で育てた学生が地域のIT業界に裨益することが期待されます。
(安延) 幅広いテーマを取り上げていただき、時間を大幅に延長して盛り上がりました。内田課長には、お忙しいところ本当にありがとうございました。
第2回 JASPA × JIET 合同名刺交換会を開催しました。
前回大変ご好評いただいた会ですが、今回は前回の参加者をさらに上回り、総勢150名の方々にご参加いただきました。
日 時:令和6年2月29日(木)17:00~19:00
会 場:特定非営利活動法人 日本情報技術取引所(JIET)オフィス
東京都品川区西五反田2丁目12番3号 第一誠実ビル 6階
【イベントの流れ】
・開催挨拶 JASPA 安延会長・JIET 南出副理事長
・乾杯挨拶 JIET 福本委員長
・団体紹介 JASPA広報委員会 田井中委員長
・中締め挨拶 JASPAビジネス推進委員会 石井委員長


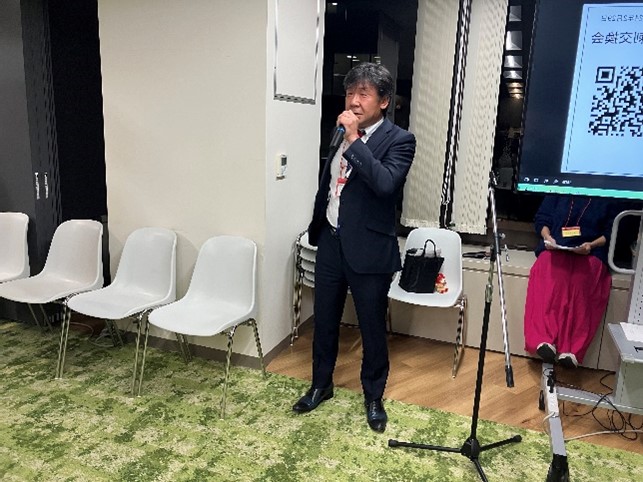
ご参加2回目方々が初回の方々をリードし、より一層交流を深める場面も多々見受けられ、今後の展開が楽しみな会となりました。
JASPA LINE公式アカウント Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ
現在、JASPAのLINE公式アカウントでは新たな友だちを募集中です!
この機会に友だち追加をして『Amazonギフトカード プレゼントキャンペーン』にご参加ください。すでに友だち追加済みの方も、もちろん参加可能です。
ぜひ、JASPAのLINE公式アカウントをチェックしてみてください。
【友だち追加方法】
https://lin.ee/SsdymDp
上記URLにスマホでアクセスするか、添付のQRコードからアクセスしてください。
その後、次のステップに進んでください:
1.LINE公式アカウントを友だち追加する。
2.登録完了メッセージを確認する。
3.画面下のプレゼントキャンペーン内の「応募する」をタップする。
これだけで、後は抽選結果を待つだけです!
【キャンペーン期間】
2023年8月1日から2023年8月25日まで
【抽選結果の発表】
当選者には2023年8月31日にご連絡いたします。
ぜひ、このキャンペーンにご参加ください。
JASPAのLINE公式アカウントでは、JASPA会員、関係者の皆様にとって有益な情報を厳選してお届けしています。
各種イベントや研修情報など、一つのタップで簡単にアクセスできます。
この特別な機会にぜひ、友だち追加をお願いいたします。
キャンペーン主催:全国ソフトウェア協同組合連合会
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
| 添付 |
| 友達追加QR |
JASPA ITビジネス創出展2022 トークセッションのご紹介
令和4年11月14日(月)に開催いたしました「JASPA ITビジネス創出展2022」における各スポンサーのトークセッションをご紹介いたします。
①多くの企業で進む「脱PRA→デジタルワーカー導入」 東京システムハウス株式会社
②LinuxによるIT人材育成プログラムの有用性 株式会社エー・アール・シー
③チャットでヘルスケアサポートができる福利厚生サービスのご紹介 アスノシステム株式会社
④本当に効果を出す人材育成施策設計の3つのポイントとは? コムチュア株式会社
⑤なぜ今サイバー保険が必要なのか 株式会社ワイズトータルサポート
【広報プレゼンツ】CSA×JITRAD合同イベント開催における 理事長インタビュー
2022年9月13日、電算ソフトウェア協同組合(以下、CSA)と中央イメージテクノロジー研究開発協同組合(以下、JITRAD)の都内某所で、合同イベントが開催されました。
Withコロナ以降、様々なイベントの中止やWeb開催を継続する組合も多い中、合同交流会に踏み切った二組の組合理事長にインタビューさせていただきました。
語り手:
太田 貴之 電算ソフトウェア協同組合理事長
堀越 正 中央イメージ・テクノロジー研究開発協同組合理事長
聞き手:
広報委員会(田井中 友香・平野 正人)

中央イメージ・テクノロジー研究開発協同組合理事長
(広報)本日は、お時間をいただきありがとうございます。早速ですが、9月13日に行われた「合同交流会」のことからお話を伺いたいと思います。9月といえば「Withコロナ」の真最中でしたよね。どんな経緯でリアル開催に踏み切ることになったのですか?あ、その前に、この「合同交流会」の正式名称があれば教えてください。
(堀越理事長)いや、ないですね。私たちもなんとなく「合同交流会」と呼んでいます (笑)
(太田理事長)そうですね、「合同」とかもついてなかったような・・・(笑)。組合間交流会、まぁ、見合いみたいな感じでやったイベントでしたね。
(広報)そのゆるい感じがいいですね(笑) JASPAの中で組合同士が集まって合同イベントを開催するのは、初めてだったんじゃないでしょうか。私が知る限り、ゴルフやイベントならありますけど、2つの組合が合同で交流会を開いた前例は、確かなかったような・・・(記憶が皆あいまいで言葉を探す広報委員・・・)、そもそも開催の経緯は?
(堀越理事長)僕が理事長になってから、組合内で何か新しい企画を立てないとつまらないな~と思ったのが発端です。そもそもJASPAって、ある一定のメンバー、たとえば「22世紀のメンバー」などは、ものすごく親密になるけれど、それ以外の人とは、年1回の賀詞交歓会くらいしか交流できる場所がないんですよね。しかも、その賀詞交歓会でも名刺交換する程度で、結局、他の組合と交われていないことに気が付いたんです。
そこで、JITRADのイベントとして、他の組合の方をお招きして「組合交流会」をやったらどうかな? ということになったわけです。イベント自体は、(各組合内の)各社の紹介や、JASPAの活動を紹介できればいいなと考えて、太田理事長にお声がけしました。
(太田理事長)今だから言えますが、9月開催ということで「JASPAフェア」の宣伝にもなったらいいな、という下心もちょっと(いや、しっかりかな 笑)ありました。会としての活動が形骸化していること、何か新しいことしたいよね、という気持ちをお互いに持っていたので、話は早かったです。まずはお互いの会社紹介をするところから初めて(だからお見合い)、ゆくゆくはビジネスにも発展してもらうような関係を築いていければ、その中でみんなが仲良くなれたらいいよねって。
(堀越理事長)確かに、JASPAで今までこういう事をしたことがなかったので、『じゃ、まずはやってみよう!』となりました。それがうまく回るようだったら、継続も視野に入れつつ、他の組合ともやってみたいと。我々が最初の事例になれたらいいね、なんていう思いもありました。
(広報) 2人の理事長の新たなチャレンジですね。実際に開催してみて、いかがでしたか?別々の組合ではありますが、同じ業界ですから、予想外の化学反応や、新たな刺激が得られたりとか・・。
(太田理事長)うちの会員企業の中では「あそこの会社、面白いね」という話はいくつか出ていましたが、いかんせん時間が短すぎました。それぞれ前に出てきて自社紹介をしたんですが、全員参加でやったので、持ち時間はせいぜい一社につき2、3分。ここは反省点でもあります。なので、実際に色々と話ができたのは、その後の懇親会でした。
(堀越理事長)あ〜、懇親会もね~、着席&コース料理にしちゃったからね、いまいち動きが悪かったよね。
(太田理事長) そうそう、テーブル席でコース料理とかにしちゃったから、それだとみんなが席に固まっちゃったかな、というのも反省点のひとつです。
(広報) いや、コロナ対策的には正しかったとは思います。

電算ソフトウェア協同組合理事長
(堀越理事長)懇親会では、各組合のこと以外に、JASPAの活動について、十分時間を取って説明しました。フェアのPRも「こんな趣旨でやってます」と飯嶋さんからプレゼンしてもらったり、太田さんの教育委員会の活動説明(セミナーの案内や助成金使ったセミナーなど)もやりましたね。
(広報) 多分、お2人自身はJASPAの中でも活発に動かれていると思うのですが、今回のように違う組合の方が集まる中でJASPAのことを話して、改めて何か違いを感じましたか?
(太田理事長)う〜ん、まずは第1回が無事終わったということで、ひとつクリアかな。そんなに急には無理でしょう。ゆくゆくはそういう成果を出したいなっていう感じですね。
(堀越理事長)今回の成果としては、「あの組合に、こういう会社もいるのか」と、知るきっかけにはなったかなと。今後はゴルフの対抗戦とか、いろいろなイベントも含めて、継続していきたいですね。
(太田理事長)そうそう、1対1(まさにお見合い 笑)で定期的にですかね。だんだんと顔見知りが増えてくれば、「今度はJASPAのイベントに参加してみましょうか」となったり、「まずは交流委員会のイベントぐらいには出てみようかな」といった感じで、徐々に輪が広がってくれるといいなと思っています。
(堀越理事長)09:24JITRADも年1回 研修旅行やっているので、もしタイミングが合えば、地方の組合の活動にも参加してみたいですね。夜の懇親会も含めて(笑)
(広報)では、交流会の話に戻しまして・・・参加者は何人ぐらいでしたか?
(堀越理事長)この時は参加がとても良くて、懇親会で24人ぐらいでした。
(太田理事長)「またやろうよ」とって言ってくれたり、「2回目はやんないんですか?」と聞いてくる会員さんもいたのが、うれしかったですね。やって良かったと思いました。
いくら合同でやっても1回だけじゃ、名刺交換して終わりになっちゃうんで、続けていくことが大切ですよね。「あ、またお会いしましたね」という感じで、コミュニケーションを取るというか、ネットワークを作る上で、時間と回数はある程度必要になってくるのかなと。我々もね、多大な時間と金を使って、今のような付き合いになってるんで(笑)
(堀越理事長)どんだけ使ったか(笑)
(太田理事長)コスパ悪いなみたいな(笑)
(堀越理事長)人間関係に効率化はないからね。
(広報)仲が良いですね(笑)

では、最後に、今後注意すべき点、懸念点などがあったら教えてください。
(堀越理事長)やっぱり、着席&コース料理が問題だったかな。
(太田理事長)そうそう、でも、さすがにこの人数で一気にわしゃわしゃ交流するのは、ちょっとだけ気が引けたというか、まだ、しづらい時期でしたね。
(堀越理事長)あの人数でプロジェクターを使うことも考えると、着席以外難しかったですよね。でも、ようやくコロナも落ち着いてきたし、次回はもっと自由に動けるスタイルを考えたいね。
(太田理事長)ですね。立食のビュッフェスタイルもいいですよね。どちらかというと、懇親会の方がメインだったりするんで、フランクに会話が弾むような会にしていきたいな。
(堀越理事長)あんまり仕事、仕事になっちゃうと、それはそれでね・・・。
(太田理事長)そう、ここから各会員企業さん同士が繋がってくれればいいと思うんですよ。今回のような場の中で、「あ、こんなことやってらっしゃるんですか」とか、「今度、個別でお邪魔していいですか?」といった感じで。そんな出会いのきっかけを、我々組合側が提供できればいいんじゃないかなって思います。
【最後に】
お忙しい中、太田理事長、堀越理事長にお集まりいただき、色々と前向きなお話を伺う事ができました。「JASPAで良かった」と思える活動を広めている2人の若き理事長の今後のご活躍を、広報としてもとても楽しみにしています。本当にありがとうございました!
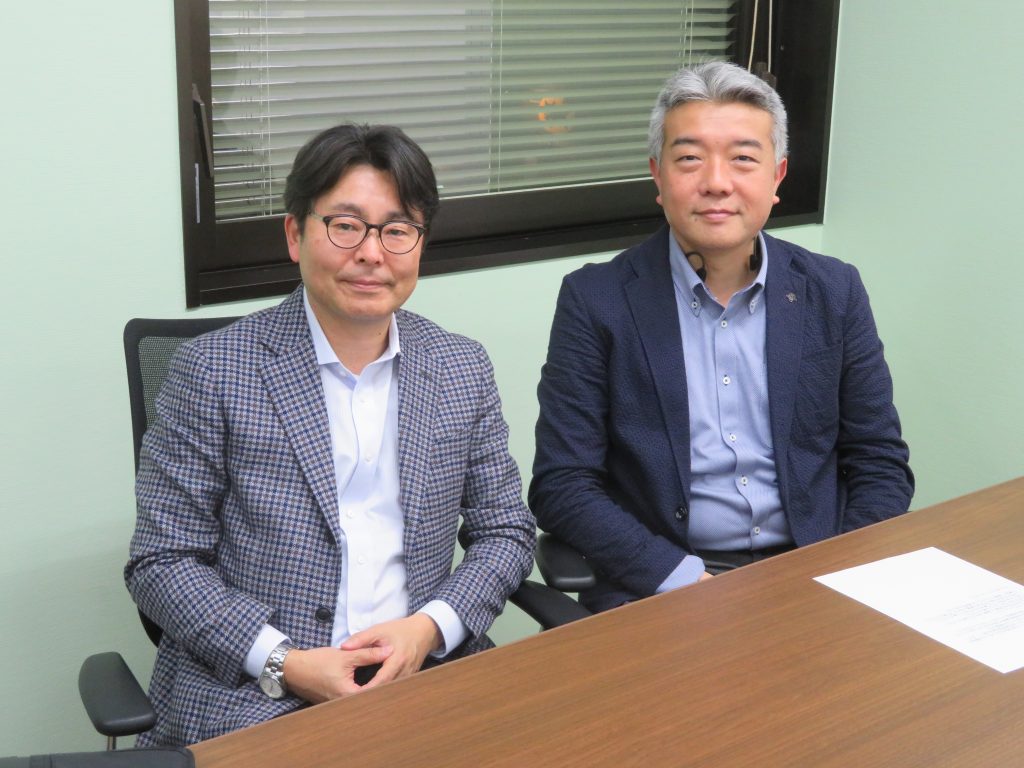
2023年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
令和5年2月22日
各位
全国ソフトウェア協同組合連合会
2023年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
全国ソフトウェア協同組合連合会では、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構・東京支部生産性向上支援センター(以下「センター」という)から「会員企業に対する生産性向上支援訓練実施業務」を受託し、会員企業が抱える生産性向上に関する人材育成上の課題やニーズに対応した訓練を実施しています。
今般、センターが実施する2023年度生産性向上支援訓練オープンコースについて情報提供させていただきます。下記URLをクリックするとオープンコース一覧のほか、リーフレットをPDFにてご覧になれます。
◆オープンコース受講者募集リーフレット(2023年4月~9月開催)PDF
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/q2k4vk000000w0zf-att/q2k4vk0000053jhp.pdf
◆オープンコース一覧表(2023年4月~9月開催)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/open202304.html
オープンコースとは
幅広い企業の在職者(パート・アルバイト含む)向けに実施する公開型訓練コースです。
生産管理、IoT・クラウド活用、組織マネジメント、マーケティング、IT新技術の理解などあらゆる産業分野の生産性向上に効果的なカリキュラムをご用意しています。
*受講希望の方は、「オープンコース受講申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてセンター宛てお送りください。オープンコース申込書はホームページからダウンロードした様式、リーフレット裏面の様式をご利用ください。
*各コースのお申込みは、以下オープンコース受講者募集リーフレット(2023年4月~9月開催)PDFに受講申込書を添付していますので、必要事項を記入の上、生産性向上支援センターまでお申込みください。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/q2k4vk000000w0zf-att/q2k4vk0000053jhp.pdf
以上
JASPA経済産業省 情報技術利用促進課 課長との座談会

日時:2022年12月14日(水) 10:30~12:00
出席者:
【経済産業省商務情報政策局】
内田 了司様(情報技術利用促進課長)
和泉 憲明様 (情報経済課アーキテクチャ戦略企画室長)
【全国ソフトウェア協同組合連合会】
安延 申(JASPA会長/首都圏ソフトウェア協同組合理事長)
林 知之(JASPA副会長/埼玉ソフトウェア事業協同組合理事長)
太田 貴之(JASPA副会長/電算ソフトウェア協同組合理事長)
リスキリングが一丁目一番地

JASPA会長/首都圏ソフトウェア協同組合 理事長
(安延) DXが喧伝されるなか、Web3.0とかクラウド等のような新技術への対応について、経済産業省はデジタル政策においてどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
(内田) 2018年に経済産業省が出した「DXレポート」が「2025年の崖」を指摘したように、わが国は諸外国と比べてデジタル化が大きく遅れてきたのは事実だと思います。それから4年、あちこちでDXという言葉が聞かれるようになり、ベンダー企業やIT企業でなく一般の企業でもDXを進める動きが見られるのは、官民を挙げた運動の成果だと思います。
DXを進めていく上ではもはやIT企業だけでなく、ユーザー企業自らが人材育成をして社内を変えていかなければならないということは一般化・常識化したと思います。国際競争力の指標も低迷する中で、ようやく国際競争の入り口に立ったといえるのかもしれません。デジタル人材が慢性的に不足しているのは、こうした構造変化に対して実際の人材供給構造が変わっていないことの果でもあると思います。そうであれば、場当たり的ではなく構造的に対処していくことが不可欠になります。
岸田総理が所信表明演説や国会答弁などで述べられているように、多方面で「リスキリング」という言葉がクローズアップされています。実は昨年度から厚生労働省に3年間で4000億円の人への投資予算が付いていたのですが、今年はこの人への投資支援が5年間で1兆円に拡充されました。デジタル業界だけでなく、カーボンニュートラルのような課題も含めて世の中の構造変化がかなり起きており、これまでの人材のスキルでは対応できないような社会経済の大きな地殻変動にリスキリングを通じて対応していくためのものです。その筆頭がDXであり、政府内でもデジタルのリスキリングをどうするかということが先行して議論されています。
国の政策としては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が改訂されて「デジタル田園都市国家構想」に変わり、デジタル推進人材を5年間で230万人育成するという目標を掲げました。これは、社会人として働く全ての人がデジタルリテラシーを身に付けた上で、その中でDXを進める人材はさらにスキルを伸ばしていかなければならないという目標です。 皆さんご案内のとおり、高校で「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」が必修となりました。
2025年には大学入学共通テストの科目に「情報Ⅰ」が加わります。「情報Ⅰ」の試作問題を見ると、ITパスポートレベル以上、情報処理技術者試験の基本情報技術者試験相当かそれ以上の内容です。すなわち数年後には、既にITパスポートや基本情報技術者試験に合格しているレベルの新社会人たちが世の中に出てくるわけです。
そういった人たちは本当の意味でのDX Ready人材として世の中に出てくるので、むしろ社会に今いる我々こそ、その人たちと同等以上のスキルを身に付けないとデジタル社会を支えることはできないことになります。若い人たちがスキルを身に付けて社会に出ていくのは良い改革であり、これは長年の関係者の努力が実を結ぶ時代になるわけです。それを先導するのは皆さんの業界であり、それを支えるのが政府の役目ではないかと思います。
情報科目の意義
(林) 学校の授業に情報科目が入るのは絶対にいいことだと思うのですが、現実の社会でどれぐらいの効果があるのでしょうか。
(内田) リスキリングのための様々な制度的支援を行っています。デジタル人材育成のプラットフォームやポータルサイトを立ち上げたり、実践的な課題解決能力まで踏み込んだプログラムを提供したりしていますが、企業の方々に、どんなスペックの人材が必要なのかと聞くと、意外と多くの企業が、机上の学問ではなく実践力や課題解決力、さらにいえば課題に当たったときに最後までやり抜く胆力が必要だとされています。結局は入社してから教育するのだから、別に教育分野は問わないという企業もあります。
一方で、幾つかの企業は完全にジョブ型雇用に移行していて、この職種にはこのスペックが必要だということを明確に示した上で社内外から人材を募集しています。そういった企業は、ミッションが明確なのでスペックで人材を求めています。今はその2種類が混在している状況です。
(和泉) 本来、プログラミングなどの情報系の科目はコンピュータサイエンス(計算機科学)の一部なので、サイエンスとしての体系に位置づけられるべきところ、スキルとして教えようとしていませんかね。というのは、プログラミング言語は、いわばランゲージを教わるようなものであり、第二外国語を学ぶようなものと考えられています。しかし、現場では外国語を教えるにもかかわらず「辞書と文法書だけを与えたら明日から外国文学がすらすら書ける」とすませている、という古くからの指摘もあります。リスキリングといいながら、第二外国語を学ぶと何が出来るようになるのか、何を対価として得られるようになるのか、というイメージも具体化されないまま、カリキュラムが組み上げられている可能性があります。(計算理論やモデル理論を学ぶことなくプログラミングだけ学んでエンジニアになるということは、歴史や文化を無視して外国語だけ習得して外交官や通訳になるようなことなのです。)構造的欠陥はそこだと思います。
わが国の情報教育に関する歴史的な経緯として、コンピュータサイエンスの教育を日本で実施しようとしたときに、理学の一部として実施されず、論理回路や適応フィルタとの親和性で、工学の一部として定着したと聞いています。なので、日本では、計算機科学・情報科学ではなく、情報工学というエンジニアリングの分野としてスタートしたそうです。コンピュータサイエンスの学者の一部では、課題の根っこはそこではないか、と会話されることがあります。
(安延) いつまでも情報やデジタルの時代とは限りませんし、次にまた何かすごい技術革新が起きるのかも知れません。ただ、こうした大きなうねりのような技術革新の際は、現場の大学にまかせていても、古い先生方が議論して決めるわけですから、革新には対応できないように思います。 例えばスタンフォードに行くと、コンピュータサイエンスの立派なビルが建っていて、その主たるスポンサーはマイクロソフトだったりアップルなどです。そしてコンピュータサイエンスの先生をどう選んで、どのように運営するかというのは、これらのスポンサーの意向がちゃんと反映されます。日本の場合は、その学部にいる上の先生方が過去の経験で決めているように思えますが。
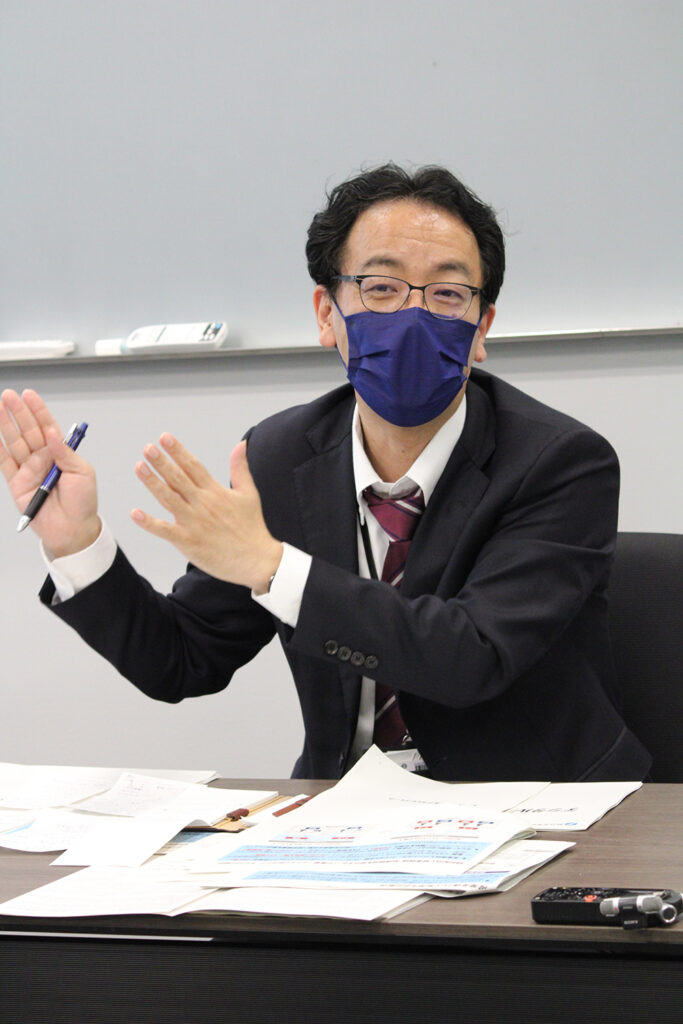
経済産業省 情報経済課アーキテクチャ戦略企画室長
(和泉) プログラミング教育や情報教育がどう役に立つのか、という議論が十分ではない中で、リスキリングも含めたライフサイクル全体で人材の入り口と出口を俯瞰し、どういう教育をどこにどう配置すべきかというのを考えたのは人材育成政策としては初めてではないでしょうか。そういう意味では、いい取り組みが立ち上がったと考えていただきたいですし、この取り組みをより良いものにするために、業界側からも「こういう人材が欲しい」「(そういう人材育成のために)こういう教育・カリキュラムを用意してほしい」という議論が寄せられると良いですね。

JASPA副会長/電算ソフトウェア協同組合理事長
(太田) 高校教育の中に「情報」が入ったことはすごくいいことだと思っていて、中身を直す必要があればこれから変えていけばいいと思っています。
商業高校などではだんだんパソコンや情報の教育にシフトしているのですが、高校ではIT業界に就職させたいし、高校生のなりたい職業ランキングの上位にはITエンジニアが入っています。しかし企業側が「高校生は教育が大変で」などと言って採らなかったりするのです。高校はどんどん送り出したいのに、受け入れていない企業があるのを目の当たりにしたときに、このギャップは何だろうと思いました。
せっかくアイデアを持っていてもルールや法律が足かせとなってできなかったり、これをちょっと外しただけで流れが大きく変わるだろうということがたくさんありそうな感じがしています。例えば高卒の就職に関するレギュレーションもそうでしょうし、いろいろなことがあるのだろうと思います。
(内田) まさにGIGAスクールの実現なども含めて、小学生のときからデジタルツールを使いこなしている子たちがいることに幾つかの企業は既に目を付けていて、別に正社員でなくても、そういう子たちの力を放課後に使うようなことをしているところもあります。それがもう少し進んで高校生、大学生になってくると、大手企業に行っても自分の能力が生かせないからということで、例えば量子コンピューティングを大学院で学んだ学生が副業で量子コンピューティングのスタートアップを友人と一緒に立ち上げたりしています。そういった能力のある若者はすごく増えてきていると体感的に思います。その若者たちの行き先がないというか、本当はあるのに社会の側がそういった能力を活かせていないところがあると思うのです。
デジタル人材の育成体制
(内田) その背景として、先ほど来お話ししているDX待ったなしという機運や人がDXを進めるための人材が足りないという状況があります。政府は旧来、人への投資をあまりしてきませんでした。教育は文部科学省がやっているし、リスキリングは会社がやるものであって、それに税金を投入することは長らくありませんでした。ここ最近、人への投資に対してお金が付いてきたのは大きな変化で、それをもたらしたのはデジタル化を中心と
した社会構造の変化であり、それに対応していくためには人に投資しないと駄目だろうという認識がようやく定着してきて、政府の政策が強化されてきたと思います。
リスキリングに1兆円支援という状況になりましたが、どのような人材を育成していくかのディテールはまだこれからです。そこはマーケットの声を聞いて設計しながら決まっていくものだと思うので、ぜひ明確に業界でも個社でも示してもらえばと思います。
デジタル人材について言えば、これまでIT業界にはITスキル標準(ITSS)がありましたが、これはIT時代のスキル標準であり、今はDX推進に必要な人材類型について必要なスキルを定義したDX推進スキル標準というものを議論しています。これはITSSに取って代わるものではなく、ITSSにプラスした新たなスキル標準です。ITSS的なスキルは引き続き企業内のシステムエンジニアとして必要とされると思いますが、それだけではDXは実現できません。そのため、DX推進スキルとして5類型のスキルセットを提示します。
企業と話をしていても、DX人材が必要といわれていながら企業側もどんなスキルを持った人を採用したらいいか分からなかったり、企業内でリスキリングをしてもどういった人を育てたらいいか分からないという声があり、DXに必要なスキルセットの大枠を国に示してもらえれば、それを中心にして人を育てたいという企業が結構多いのです。デジタルを中心とした人材育成・供給に関してはようやく大きな流れとなり、若年層のスキルの高度化や社会人のリスキリングの議論が盛り上がってきています。そこで、文部科学省と共同でデジタル人材育成推進協議会を立ち上げました。スキルが上がった若年層が大学に行ったとしても情報学部の定員だけが未だに少ない実態があり、社会が求めるだけの人材供給ができていないという問題意識を共有しています。

経済産業省 情報技術利用促進課長
(安延) 教える人が足りないから、学部の定員が増やせないのですか。
(内田) 基本的に学部学科はスクラップ&ビルドなので、情報学部を作ろうとすると文系のどこかをつぶさなければならないという事情があります。
(安延) ニーズが増えてくると徐々にではあるけれどもちゃんと変わっていくのがこの国のいいところだと思っているのですが、情報の場合は人が足りないと、ずっといわれているのに全然増えないのはなぜだろうと思うのです。
(内田) 大学側も問題意識は持っているものの、なかなか変わらない現状を何とか変えていくための議論をする場がこの会議体です。新分野の教育をできる教員が十分にいないという問題もあります。経済界側も地域レベルでできることはたくさんあって、人材は待っていれば来るわけではなく、地域の教育機関と連携しながら育てていかないと生まれないので、これは地域でも大学でもあらゆるレイヤーで取り組む必要があるでしょう。
政府がとるべきデジタル政策とは
(内田) 政府がやるべきことと民間がやれることの棲み分けを常に意識したいと思います。デジタル人材育成について言えば、民間マーケットでリスキリングなどの人材供給の仕組みが不十分であれば、その仕組みが上手く回るように限定的にお手伝いすることです。実際、人材供給やリスキリングをするマーケットの人たちと話していると、足下の人材不足を受けて小さなパイを食い合っているだけで、市場拡大に向けたビジョンがあまり見えないのです。ですから、リスキリングや人材供給のマーケットがサステナブルになるように、もっとパイを拡大していこうという話をしています。
その上で、スキルアップした人が正当な対価をもらえるような需給のバランスがマーケットメカニズムによってワークするところまでお手伝いすることが役目だと思っています。そうした視点で取り組んでいるので、個々の人材のスペックがどうとか、こういう経験を積みなさいということに口を出すつもりはなくて、まずは決定的に足りていないボリュームゾーンをかさ上げすることをお手伝いするのが基本的なスタンスです。
足下では、引き続きものづくり補助金やIT導入補助金等を使ってようやく社内にシステムを導入したような人たちが世の中にはたくさんいるわけです。本当はそうした人たちのマーケットも人材育成のマーケットに取り込んで、60歳になっても新しいスキルにアップデートして働けるようにする状況を作れなければ、日本の産業はものづくりも含めて永続しないでしょう。
小学生から高齢者まであらゆる社会の各層がDXの支え手・担い手になることはデジタル社会の共通課題だと思っていますし、その中で特に優れた人たちをどう使っていくかというのは皆さんの課題だと思います。

(林) だから、きっかけですよね。変わろうとしている人はたくさんいて、その人たちをいかに1段階上のレイヤーに上げるかでしょう。 (安延) 政府でなければできないことを政府がやることがすごく大事だと思っています。日本の制度が変わるスピードを考えると、例えば、外国人の雇用や生活にまだまだ障害が多いし変化が遅い。
アメリカにしても先端技術を支えているのはアメリカで生まれた人以外の方が多かったりするのであって、日本もその方向に向かわせることは国にしかできないですよね。
(和泉) 社会インフラが刷新されつつある今、産業構造・企業構造がどう変わるのかが問われていると考えています。古い部分はなくなればいい、という意見もあるのだと思いますが、そもそも、変革は誰がリードするのかという議論が重要だと思います。
(安延) ビジネスをやっている以上。われわれはもうけたいし生き残りたいので、最後の結果責任は業界に来る
のは構わないのですが、古い人たち、変わろうとしない人たちの意見ばかり聞いて彼らが有利になるような仕組みを作る、あるいは仕組みを変えようとしないのはやめてほしいのです。
(和泉) 私個人は、古い人たち、変わろうとしない人たちを有利にする仕組みには興味がありません(し、検討するつもりもありません)。ただし、ブロックチェーンありき、Web3.0ありきという新技術ありきの議論は、政府のインテリジェンスとしては恥ずかしいと考えています。なので、社会システムがデジタル変革でどう変わっていくのかという全体像を可視化した制度設計がとても重要です。
(内田) デジタル庁ができるまでは、そもそもガバメントクラウドという発想すら全くなかったものが、半導体戦略の一部としてガバメントクラウドを立ち上げて、少なくとも経済安全保障上重要なものや政府データはガバメントクラウドでやっていこうということになったわけです。そして、それより大事なことは、半導体戦略の中で、スマホのチップなども他律的に購入するだけだったのが、それこそ自分たちで2ナノを目指して英知を結集し、アメリカと連携して技術提供しようという話にまでなっています。この流れは、コロナや地政学上必要に迫られてやっている部分もありますが、今後も継続していくと思います。
その先には、データ取扱量は飛躍的に伸び、計算能力も高まれば消費電力も高まるということが起きるわけで、これまでにないような新技術が現場でも実装されていきます。今後、さまざまなコンピューティングパワーに支えられた新しい産業が生まれるときに、その担い手がいることが重要になります。
だからこそ、全国民が少なくともデジタルリテラシーを身に付けた上で、新しいサービスを使いこなすことが市民レベルでも常識化し、更にはデジタル社会をオペレートするような人材を育てていく必要があります。ですから、少なくとも皆さんのようなIT業界が率先して新分野に継続的にチャレンジしていかないと、これから作っていこうとしているコンピューティングパワーが生かせません。将来を見ながら人材をどう育てていくかというのは、官民両方の課題だと思います。
中小企業への支援
(太田) われわれJASPAは中小企業の団体ですから、自社の経営規模から考えるとどこまで投資できるのかというときに、将来に向けてこんなところを目指しているというロードマップが分かったり、ルールや法制度の緩和だったりすれば、それを踏まえて、どこにどういうチャンスやリスクがあるかを見ながらやっていかなくてはいけないと思います。
その中で、副業や兼業をもう少しやりやすいルールにすると良いと思うのです。われわれIT業界の人材が他の業界で働きやすくし、他の業界のことも見やすくできれば、DXのアーキテクト人材やリスキリングにもつながるのではないかと思います。

JASPA副会長/埼玉ソフトウェア事業協同組合理事長
(林) 教育に関する補助金にしても、受講料の一部を補助するのではなく人件費を補助する形にしてほしいのです。
(内田) 厚生労働省と連携して、教育補助の部分は相当密接にできるようになりました。端的に人への給付や企業への補助金は、デジタルのリスキリングに連動して使えるようになっています。ただ、大事なのはビジネスを回しながらスキルアップしていくことでしょうから、単に教育補助だけでなくビジネスの継続という観点から補助を付けてほしいというニーズは強いのだと思います。
(林) 昔、国鉄からJRになるときに大金を使って国鉄職員の方々にリスキリングしましたよね。それも国が全部費用を出していたわけです。給料や教育費用ぐらいのことは補助してもいいのではないですか。われわれ業界だけでなく民間企業でもITやDXなどを教育する学校を作って、費用も給料も全て補助したらいいと思うのです。
(和泉) 古い人、変わろうとしない人のための支援が必要なのか、変革をリードする人のための支援が必要なのか、どちらに対する支援が必要なのでしょうか。
(安延) どちらでもないと思います。簡単にたとえ話をすると、わが組合で人材育成の特別クラスを組んで20人募集します。そして、業界の未来ビジョンを経済産業省から来てもらって2日間話してもらうとします。受講料が1日5000円だとすると2日間で1万円で、厚生労働省が半額補助するとして5000円×20人×2日=20万円の補助が出ます。だけど、その補助が出ても1人5000円は必要な訳じゃないですか。加えて、人を出している企業からすると、その人たちが2日間職場から外れるわけです。中小企業からすれば、「教育効果が最大の人材を出す」のではなく、「2日間出してもいいやつを出しておけ」となるのが普通ですよね。つまり、せっかく補助しているのに、おそらく狙った効果は上がらない。
だからといって現在の厚生労働省の仕組みからすれば丸ごとそういうお金は出せないということなのでしょうそ
れなら、デジタル化、リスキリングをそんなに強調するなら、デジタル人材育成の場をJRのときのように5年でも10年でも期間限定で作って、「今だけですよ」と言ってやってくれればと、われわれも必死になって人を出して教育してもらう気になるかもしれないし、同じ金額でも政策効果は上がるのではないですか?
(和泉) その構造は取引慣習とも関係していませんか。例えば、ユーザー企業はシステムを止めたくないけど、より安いシステムに乗り換えたいし、さらに先進的なシステムに変わっているとうれしいし、しかもノーリスクで、という都合の良い考えと似ているような気がします。IT投資とは考えず、毎年の経費の中でできればいいと。以前、ユーザー企業がもっとIT投資をすべきではないか、ITはコストではなく成長の道具ではないか、という会話をしていたときに同じような議論をしていた記憶があります。
(林)そこはわれわれ業界も一般企業も一緒で、大企業で付加価値が高い、あるいは余裕があるところは投資と思って実行できますが、中小の場合余裕はないし、付加価値が明確でなければ投資はできないので、それは国の役割として底上げしていくことになるのかもしれません。
(内田) どこが適正ラインかというのはなかなか難しい議論なのですが、和泉室長の言うとおり、人に投資することは別にコストではなくて、むしろ業務の高度化や新事業分野に進出するために必要な経費であり、むしろプラスの経費だという考え方もあります。だから、その適正ラインは個社によって異なり、実際大企業と中小企業では人的リソースやキャパシティが当然異なるので、この人が抜けたら業務が回らないという現実があることも理解します。
(林) それから、手続きですよね。面倒な手続きがたくさんあって、補助金申請は社労士に頼まなければならないし、不正が行われる可能性もあります。

(内田) 補助金もそうですし、教育訓練給付もリスキリングを振興する立場で一緒にやっているのですが、いざ使うとなるとハローワークに行かなければならなくて面倒な手続きがあるのは事実です。
(安延) つまり、「リスキリング」、「新しい技術の世界に合わせた人材」と言いつつ、その政策を提供する仕組みは、旧態依然の昔の仕組みということです。他方でアジャイルガバナンスということもおっしゃっているわけですが、はっきりいって全くアジャイルではありません。象徴的に、これは良かった、便利になった、有効だったというものが10個あれば、同じやり方で・・となって、あとは政府の仕組みとして転がっていくではないですか。それを最初から全体でやろうとするから、カバレッジばかり拡がって、成果的には、全部が中途半端になってしまっているように思えます。だから、先ほどデジタル人材を230万人育成するとおっしゃっていましたが、難しいのではないかと思った理由の一つは課長が「ITSSは残して」とおっしゃっていた点です。本当にITSSを残してもいいと思っておられますか。(内田) 今はまだITエンジニアが必要とされる場面がたくさんあります。
(安延) 昔、情報処理技術者という制度があって、今のITSSに移行するときも、新しいスキルのスタンダードを導入していかないといけないという思いは同じだったわけです。しかし、古いスキルのままではいけないから、スキルのバージョンアップをするために更新制を取り入れようとしたときに、誰が一番反対したかというと、古い資格を持っている方々だったのです。ですから、こうした政策の更新には本当にご苦労されるのは理解できますが、その代わりに、古い仕組みを残しておくと、どうしても古いスキルが刷新されないまま幅を利かせるという状況も発生しやすいのではないかと心配されます
(内田) DXが加速するにしたがって新しいスキルセットに移行していきますが、移行している間に新技術が出てくることによって更に新しいスキルも変更を求められてくると思うのです。新しいスキル標準に関しては、ユーザーのフィードバックも得ながら定期的に見直したいと考えています。ですから、リジッドに作り込まないで、むしろアジャイルに回していけるように、内容も詳細基準まで書き込まないで、ロールや任務を定めて、それに必要なスキルセットはこういうものだという星取表を逐次見直すことを考えています。
(和泉) 例えば江戸から明治に変わるときに、街道を往来する人の体力なのか、駕籠を担ぐためのノウハウやメンテナンスのためのスキルなのか、駕籠屋や飛脚がビジネスを刷新するとしても、いろいろな課題や変革があるわけです。その上で、駕籠屋が自動車産業に変わるような形の支援なのか、飛脚が自動車を運転するスキルとしてリスキリングするのか、いろいろな層で変化があるわけです。ただし、ここで大事なことは、東海道や中山道の往来を議論するのではなく、道路交通網や鉄道網などの社会インフラが刷新されるイメージを共有することです。私が再三申し上げているのは、中小企業といってもどのパーツのことを言っているか分からなくなるので、どこの担い手のどういう変革を目指すべきかが大事と申し上げているのです。
(安延) それは、中でちゃんとカテゴライズしておられるのではないのですか?
(和泉) ということで、まずはその全体像が重要ということです。
(内田) 新しいスキル標準では、全体像に加えて、どういうスキルセットが必要かというところまでは書き込みます。例えば、ソフトウエアエンジニアであっても少なくともデータサイエンスの基礎は理解しておくべきだというレベルのことは書き込みます。
(林) 建設業界の構造も似ていて、デザインする人、設計する人、施工する人に分かれるので。
(安延) 建設業界とわれわれが最も違うのは、建設業界は構造変化が起きていませんから、戦後ずっと同じスキルセットが通用する部分が相当あります。しかし、残念ながらわれわれの業界ではそうではありません。だから、イノベーションが起きているか起きていないかという違いがあって、イノベーションが起きていない分野は無理をして変える必要はないと思います。
(和泉) 今の議論は非常に分かりやすいですね。(技術に詳しくない人は)建設業にイノベーションが起きていないと思うかもしれませんが、例えば、ゼネコンとしては(業界構造は同じかもしれませんが)同じようなビルを建設するとしても工法や構造には大きな変化があるわけです。他方、小さな建築物なら変わっていないものもあるかもしれません。そういう中で、何のためのリスキリングが重要かという議論は注視しないといけないでしょう。
マイナンバーカードについて
(林) マイナンバーカードの普及率はかなり上がりましたが、ちゃんと機能するのでしょうか。
(和泉) 個人に対してIDは以前から割り振られていますし、個人がサービスの対象から漏れないようにIDが活用されています。逆に、IDを活用せずに個人へサービスを提供する方法は世の中にありません。ただ、今の議論は「カード」という物理的媒体が象徴のように扱われています。しかし、あくまでもカードは鍵であって、顔認証をはじめとする指紋や虹彩などのバイオメトリックスを含んだ鍵にすれば、カードをなくそうが何をしようが個人番号とそれにひもづいた情報は正しく守られます。
(安延) IDの集約は技術的には当然できるわけですが、今いわれているのはいろいろなカードの集約であって、カードを一緒にする部分は今後どうなっていくのでしょうか。
(林) それから、日本の印鑑制度はどうなるのかという問題もあります。
(内田) マイナンバーカードはデジタル庁だけでなく、各省庁の手続きをオンライン化する前提で普及が進んでおり、その中核がマイナンバーということになっています。例えば、行政手続きで戸籍謄本・抄本が必要なときに本籍地まで行かないといけないわけですが、それが不要になるようなシステム開発と制度改正はここ数年で進めます。
(安延) そうした全てのプラットフォームにおいて、このIDは信用できるのだというものがみんなに普及すればいいのだと思うのですが。
(林) 日本はいろいろ決めるのに時間がかかりますよね。
(和泉) 結局大きな理想を目指しても、その理想をどのように実現すると良いのかを具体化するまでに莫大な時間を要することを考えると、変革を達成するためには、目の前の課題を地道につぶすことが近道です。
ただし、目の前の課題への対応策が試行錯誤にならないように、こういうインフラを作って、こういう方向に行くのだという議論を、業界の人たちともっと共有しないと、私たちはその方向を本当に目指して良いだろうかという合意形成ができないわけです。
言い換えると、政策としてのボタンには、押せるボタンと押せないボタンがあるのですが、押せるところは少しずつでも確実に押していって、目指すべき方向に向かっていきたいと考えています。
(内田) まさにマイナンバーの将来可能性については、デジタル庁はもう少しオープンに考えていると思いますが、結局それを受け入れるかどうかを判断するのは国民なので、端的にデジタルのリテラシーがあるかどうかだと思います。

(安延) そうですね。ただ、メディアが煽ることもあって、そこは個人的には悲観的ですが。
(内田) 結局、リスクとベネフィットをもう少しバランスよく考えるようなマインド、デジタルによってもたらされる恩恵を正しく理解し、社会もそういうふうに変わっているし、自分たちもそれを受け入れなければならないというリテラシーを身に付けるという意味でも、今のリスキリングや学び直しは非常に大事な意味を持つと思います。
もちろん社員の確保や教育も大事でしょうけれども、その周辺にいるユーザー企業や顧客、もっと言えばその先の個人のユーザーまで、リテラシーを身に付けられるかどうかがデジタルマーケットが盛り上がるカギだと思いますし、マイナンバーのようなものを通じて日本が世界にキャッチアップしていくのだと思います。皆さんと一緒に取り組んでいくデジタル人材育成の話は、そうしたより広い意味も持っていると思います。
JASPA会報誌発行中止のお知らせ
令和4年12月23日
各位
JASPA広報委員長
田井中 友香
JASPA会報誌発行中止のお知らせ
毎年1月に恒例で発行してまいりました「JASPA会報誌」ですが、令和5年より発行を中止することになりましたのでお知らせいたします。今後は、随時ホームページにて情報を公開いたします。(https://www.jaspanet.or.jp/)
なお、恒例の経済産業省 情報技術利用促進課 課長との座談会につきましては、来年1月19日(木)にホームページにて公開する予定です。
また、各組合の情報につきましては、「会員組合紹介」ページにて公開しております。
こちらは、各組合様より、更新依頼があれば随時更新いたします。
(https://www.jaspanet.or.jp/member/)
以上
ホームページをリニューアルしました(JASPA)
各位
JASPA広報委員長
田井中 友香
ホームページをリニューアルしました(JASPA)
このたび、全国ソフトウェア協同組合連合会(JASPA)のホームページをリニューアルさせていただきました。 https://www.jaspanet.or.jp/
今回のリニューアルのポイントは、以下の通りです。
〇ポイント1 シンプルに新しい情報に目が行く構成
各委員会・組合からの発信をシンボル化し、誰から・どこからの情報かわかりやすくしました。
〇ポイント2 情報発信とSNSを連携。
JASPAWebサイトで発信を行うと、JASPAオフィシャルFacebookに自動で掲載されます。JASPAオフィシャルFacebook:https://www.facebook.com/jaspanet
〇ポイント3 各組合様Webサイトへ自動でJASPA最新情報を掲載可能。API設定は直接組合様にご連絡いたします。
〇ポイント4 委員会各ID/PASS発行できます。
委員会の皆様には、ID/PASSを発行できます。広報で管理するか、各委員会で管理するか選べます! ※各組合・委員会の皆様には別途メールでお送りします。
ますます情報が発信しやすい・情報が見やすいWebサイトへ変わりました。
ぜひ、ご活用ください。
尚、本リニューアルに伴い、従来運営しておりました「ビジネス市場」をクローズ致しました。今後、「ビジネス市場」関連の情報も本ホームページより、発信することとし、oViceを用いた商談会等も検討していきます。
今回、ホームページをリニューアルしたことに伴い、新たにバナー広告の掲載を募集いたします。詳細は、近々にお知らせいたします。
以上、よろしくお願いします。